コミュニティ政策学部って、どんなことを学ぶの?
親: 「コミュニティ政策」って、具体的に何を学ぶ学部なの?
子: 一言で言えば、「地域社会の課題をどう解決するか」を実践的に学ぶ学部だよ。高齢化や子育て支援、防災、環境、まちづくり、ボランティア活動など、地域の課題はどこにでもあるけど、それをどう支え合い、どう変えていけるかを考えるのがこの学部のテーマなんだ。
親: 政策っていうと、政治の話?
子: 政治っていうより、「地域の仕組みや制度」「市民活動」って感じかな。たとえば、福祉政策、子ども支援、地域活性化のアイデアなどを、住民・行政・NPOと一緒に考えて、実際に行動する力を身につけるのがポイントなんだよ。
「社会の課題」と「自分の行動」がつながる学び
親: 社会課題って言われても、学生に何ができるの?
子: 最初はみんな分からないところから始まるけど、授業では地域フィールドワーク、ヒアリング調査、政策提言プレゼン、地域イベント運営など、実際に人と関わりながら学ぶから、「動くことでわかること」がすごく多い。自分の言葉で語れるようになるのが強みだと思う。
親: 実習ってどんなところに行くの?
子: 自治体の地域福祉課、NPO法人、教育関係機関、環境保全団体、高齢者支援センターなど、本当に幅広いよ。実習やボランティア活動が単位になる科目もあるし、大学の外に出る学びが多いのがこの学部の魅力!
学生の雰囲気と学部のカラー
親: どんなタイプの子が多いの?
子: 「人と関わるのが好き」「地域に貢献したい」「困ってる人を支えたい」って思いがある子が多いよ。雰囲気は穏やかで、まじめで誠実な子が多い印象。福祉や教育、環境、地域ビジネスに興味がある学生が集まってて、多様性があるからこそ学びが深まる感じ。
親: 男女比はどう?
子: 男女比はほぼ半々くらい。女子は子ども支援や福祉系、男子は行政や防災、まちづくりに興味を持つ子が多い印象。みんな「誰かのために何ができるか」を考える姿勢があるから、協力しやすい空気があるよ。
公務員・NPO・地域ビジネス…多彩な進路に対応
親: コミュニティ政策学部の就職先って、限られない?
子: 全然そんなことないよ!市役所・県庁・社会福祉協議会・NPO・学校支援・福祉施設・一般企業のCSR部門・地域商社など、いろんなところで活躍できる。行政と連携して地域課題に向き合う授業が多いから、公務員志望の子は特に多いね。
親: 公務員対策はちゃんとしてるの?
子: めちゃくちゃ手厚い!SPIや時事問題の対策講座、論作文・集団討論の練習、個別模擬面接まで、1年生から段階的にサポートがあるし、ゼミの先生も親身になってアドバイスしてくれる。実習や地域活動の経験がそのままESや面接で活きることも多い!
一番印象に残っていることは?
親: 大学生活で一番印象に残っていることは?
子: 子ども食堂の立ち上げ支援に参加したプロジェクトかな。地域の人たちや行政、他大学の学生とも連携して、イベントの企画から広報、当日の運営まで全部やったんだけど、子どもたちの笑顔を見たときに「この経験は一生忘れないな」って思った。“自分の行動が、地域の力になった”実感が強かったよ。
親: 動くことで、見えるものがあるのね。
子: うん。講義で得た知識だけじゃなくて、現場で人と向き合って初めて気づくことがたくさんある。それを4年間続けられるのが、淑徳のこの学部のすごさだと思う。
受験生の親御さんに伝えたいこと
親: 最後に、淑徳大学 コミュニティ政策学部を目指す子の親御さんに伝えたいことは?
子: この学部は、社会の仕組みや制度を「教科書で学ぶ」だけでなく、「現場に出て行動する」ことで本当に使える力を育ててくれる場所です。先生方も経験豊富で、学生一人ひとりにしっかり向き合ってくれます。地域や人に関心があるお子さんには、とても良い環境だと思います。どうぞ安心して送り出してあげてください!
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
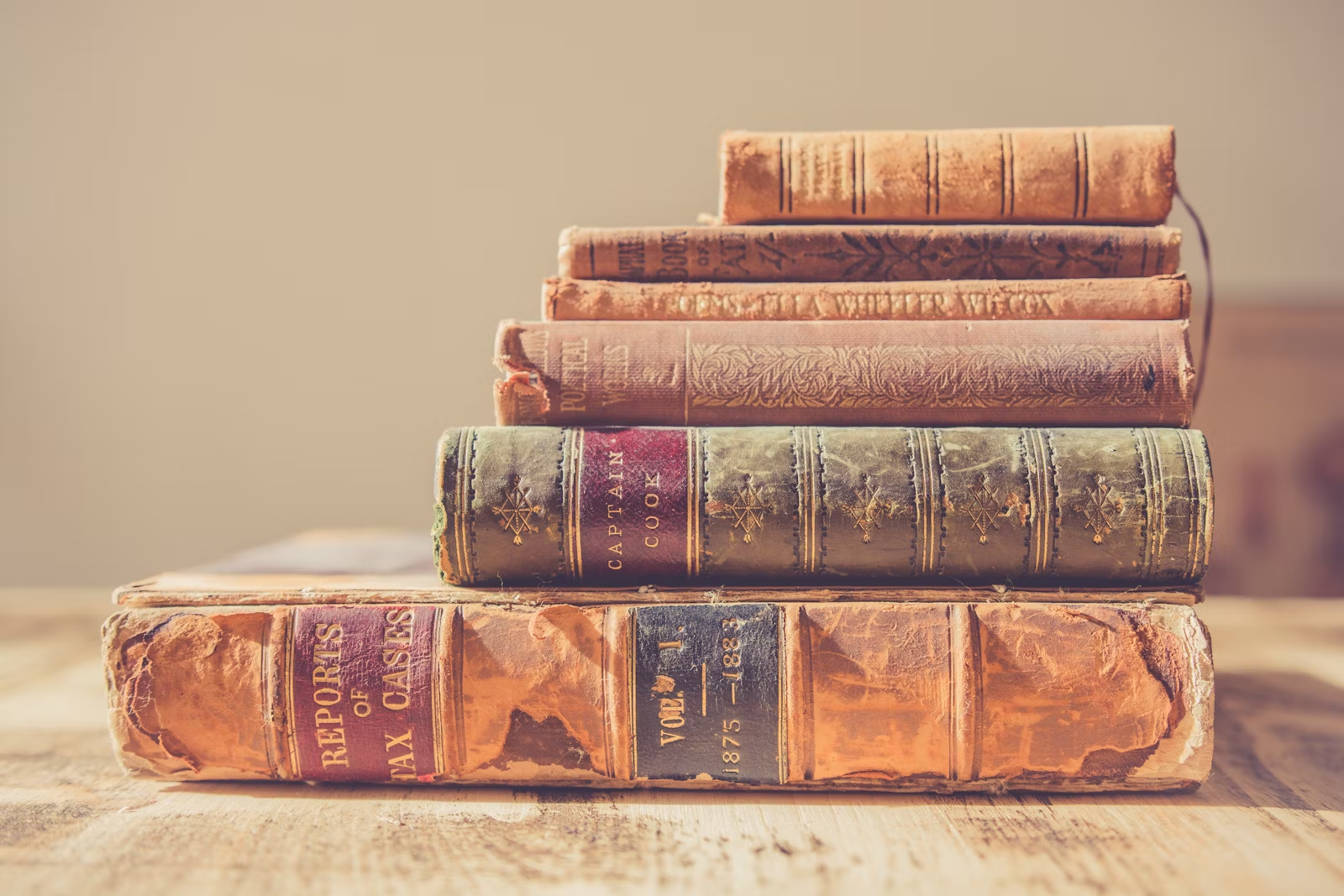



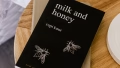
コメント