「国際食料情報学部」って何を学ぶの?理系?文系?
親: 「国際食料情報学部」って、ちょっと変わった名前ね。食べ物のこと?国際関係?それとも農業?
子: 実はその全部!東京農業大学の国際食料情報学部では、「食料・環境・文化・経済」をキーワードに、グローバルな視点で“食と社会のつながり”を考える学部なんだ。
親: じゃあ文系と理系の両方を学ぶってこと?
子: うん、まさに“文理融合型”。農学的知識や食文化、国際協力、経済・政策まで、食に関わるあらゆる情報を学ぶことで、実際の課題解決に活かしていくスタイルだよ。
学科はどうなっているの?どんなことが学べるの?
親: 学科はひとつなの?
子: うん、学科は国際食料情報学科ひとつなんだけど、学びの中身はすごく多様。主な分野としては:
- 食と文化の多様性(各国の食文化、宗教、倫理)
- 食料安全保障・国際協力(JICAや国連などの実務に直結)
- フードシステムと流通(食料の生産から消費までの仕組み)
- 環境・資源管理(持続可能な農業、水資源など)
- メディア・情報発信(食の広報、マーケティング、PR)
親: なるほど、“食”を切り口にいろんな社会のしくみを学ぶ感じなのね。
子: そうそう。「世界の飢餓と食品ロス」「アフリカ農村の支援」「地域ブランドの育て方」みたいなリアルなテーマに取り組めるよ。
授業や演習はどんな感じ?フィールド重視?
親: 座学だけじゃなくて、現場にも出るの?
子: もちろん!フィールドスタディや海外研修が充実してるのがこの学部の魅力。タイ、マレーシア、アフリカ諸国などに実際に行って、現地の農村やマーケット、NPOと連携して学ぶ授業もあるよ。
親: 学生のうちから海外に行けるのは魅力ね。
子: うん。英語でプレゼンしたり、現地の人と交流したり、「食で世界とつながる経験」がたくさんできるんだ。
学生の雰囲気は?国際系でキラキラしてる?
親: どんな子が多いのかしら?国際系って、意識高そうな感じ?
子: 意識は高いけど、“ギラギラ”してるというよりは、“じっくり型”の子が多いかな。国際協力に興味がある子、食や環境に課題意識を持ってる子が多くて、あたたかい雰囲気。女子が多めで、語学が好きな子も多いよ。
親: 雰囲気も明るそうね。
子: うん、アクティブだけど落ち着いていて、全体的に多文化に寛容な空気感があるよ!
就職はどう?国際協力の道以外もある?
親: 国際協力とかって就職が難しそうなイメージもあるけど…
子: 実は就職先はすごく幅広いよ。JICAやNPOに行く人もいれば、食品・飲料業界、商社、観光、出版、地域振興系の公務員に進む人もいる。マーケティング職や広報職も多いよ。
親: 食を軸にしていろんな業界に行けるのね。
子: うん、むしろ“どこにでも行ける”のがこの学部の強み!語学力やフィールド経験を活かして、進路を柔軟に選べるのが魅力だよ。
主な進路実績:
- 食品・飲料メーカー(広報、企画、海外事業)
- 国際協力機関(JICA、NGO、NPOなど)
- 地方自治体(観光政策、地域ブランド推進)
- 商社・流通・マーケティング関連企業
- 広報・メディア・出版関連
- 大学院進学(国際協力、地域研究、農業経済など)
印象に残った授業やプロジェクトは?
親: 今までで印象に残ってる活動はある?
子: タイでのフィールドワークかな。少数民族の農村にホームステイして、食文化と農業の現状を調査したんだ。現地の人が作った料理を一緒に食べながら、「文化と食のつながり」を肌で実感できたのが忘れられない!
最後に、保護者の方へ
親: 食や国際って、興味はあるけど将来につながるのか心配なのよね…。
子: でもこの学部は、「興味を社会に活かす力」がちゃんと育つんだ。食料問題を多角的に学ぶことで、マーケティングにも、国際協力にも、地域づくりにも応用が利く。時代に合った“応用型の教養”が身につく学部だと思うよ。
親: どんな子に向いてる学部だと思う?
子: 「食を通じて社会とつながりたい」「世界の課題を自分ごととして考えたい」「人と関わることが好き」――そんな子には、この学部はぴったりだと思う!
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
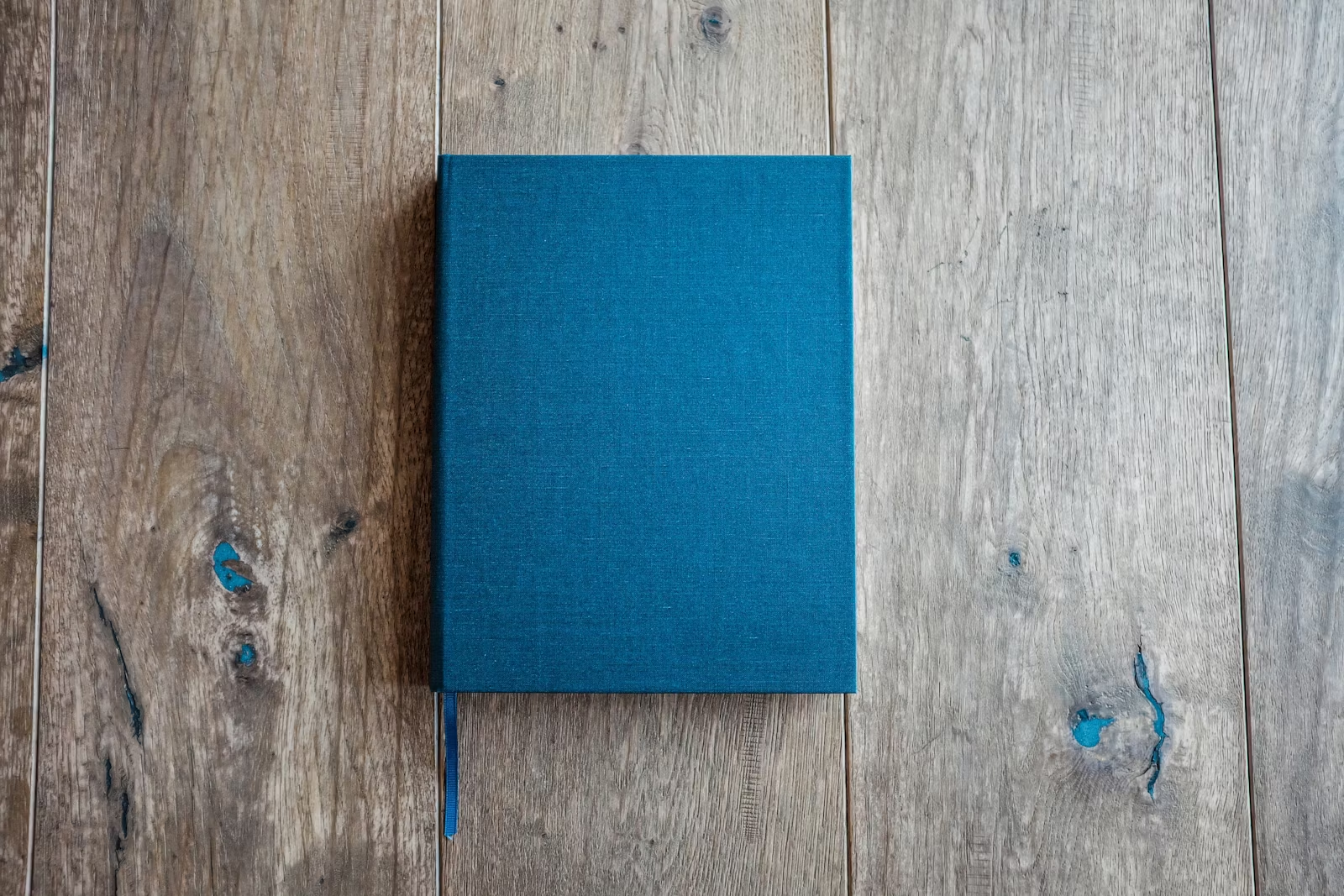




コメント