創造表現学部って何をするの?“伝える”をかたちにする学部
親: 「創造表現学部」って、名前からしてちょっと分かりづらいわね…。芸術系?それともメディア系?
子: 両方なんだよ!創造表現学部は、文章・映像・写真・デザイン・アート・メディアなど、いろんな**“表現のかたち”を探求する学部**なんだ。つまり、「自分の伝えたいことを、自分らしい方法で伝える力」を学ぶ場所!
親: なるほど。つまり“伝える”がテーマなのね。でも、それって将来どう役立つの?
子: 今の社会って、どんな仕事でも「伝える力」が必要でしょ?SNS、広告、教育、企業広報、出版、映像制作…すべて表現力が土台なんだよ。
学びの特徴①:ことば・映像・アート・社会の4領域を横断的に学ぶ
① 文章表現・ライティングを学ぶ
- エッセイ、小説、ノンフィクション、批評など多様な文体に挑戦
- 編集・出版・校正・ライター技術の実践演習も
- ゼミでは自分の作品を読み合い、批評し合う文化あり
子: 自分の言葉で「世界をどう見るか」を発信できる力が育つよ!
② 映像・写真・デジタルメディアの表現力を磨く
- 映像制作(企画・撮影・編集)、写真、デジタルアート
- Adobe系ソフト(Photoshop、Premiereなど)を実践的に活用
- 撮るだけでなく「どう見せるか」「何を伝えるか」も学ぶ
親: 技術だけでなく、“考える力”も求められるのね。
③ デザイン・アート・身体表現で“感じる”力も育てる
- 空間演出、アートインスタレーション、パフォーマンス演習
- 舞台表現、ワークショップ型授業、造形・美術演習
- 社会のなかの“美”や“違和感”を表現する力を磨く
子: 表現のジャンルが本当に幅広いから、自分に合った方法がきっと見つかる!
④ 社会と表現をつなぐ「メディア・文化研究」も重視
- 映画論、広告論、ジェンダー表現、SNS文化論など
- 社会の中で「表現はどのように機能しているか」を学問的に考える
- 批評・考察力がつくことで、深みのある作品づくりが可能に
親: 芸術だけじゃなく、社会とのつながりも意識してるのね。
学びの特徴②:ゼミ・卒業制作で“自分だけの表現”をつくる
少人数ゼミでじっくりと作品と向き合う
- 2年次後期からゼミに所属し、表現ジャンル別に作品制作
- 教員からの丁寧な指導+学生同士でのフィードバックが活発
- 映像ゼミ・小説ゼミ・写真ゼミ・広告ゼミなど多様に展開
卒業制作で“4年間の集大成”を発信
- 映像作品、写真展、エッセイ集、絵本、演劇上演、出版物など自由度高め
- 学内外で発表の機会あり(ギャラリー展示・発表会・冊子発行など)
- 「自分だけの表現ジャンル」を確立する貴重な1年
子: 卒制はめちゃくちゃ大変だけど、“一生残る作品”になるよ!
学生の雰囲気は?静かで個性的、自分の世界を大切にしている人たち
親: なんだか自由な雰囲気の学部ね。どんな子が多いの?
子: たしかに自由だけど、自分の世界を持っていて、表現するのが好きな子が多いよ。おとなしいけど芯が強いタイプも多いし、見た目は個性的でも中身はまじめな子ばかり!
親: みんな違ってて、認め合う空気がありそう。
子: そう!「正解がない世界」だからこそ、互いの表現をリスペクトする文化があるんだ。
就職・進路は?「伝える力」で社会とつながる!
主な就職先
- 出版・広告・編集・Webメディア
- 映像制作会社・写真スタジオ・デザイン事務所
- 教育・福祉・NPO(ワークショップ企画やアート活動など)
- 一般企業(広報・企画・営業・商品開発)
- 公務員(文化行政、地域活性化)
- フリーランス(ライター、写真家、映像作家)
親: 芸術系って進路が不安定なイメージだけど…意外と広いのね!
子: 表現力+文章力+ITスキルって、企業の広報や広告でもめっちゃ重宝されるんだ!
資格取得・進学も対応!
- 中学校・高校教員(国語・美術)
- 図書館司書、学芸員
- 大学院進学(表現文化・メディア学・デザイン分野)
親: 教員や学芸員も目指せるのはいいわね。
子: 表現を“教える側”として活かす道もあるから、将来の選択肢は本当に多いよ!
保護者の方へ〜こんなお子さんにおすすめ!
親: 「表現を学ぶ」って、とても深くて柔軟な学びなのね。
子: うん、だからこんなお子さんにぴったりだよ:
- 書くこと・描くこと・つくることが好き
- 表現を通じて人とつながりたい
- 自分の感性やアイデアを活かして働きたい
- 正解のない問いに取り組むのが好き
- 地道な制作・発表にも前向きに取り組める
親: “好き”を本気で学んで、それを“仕事”に変える学部なのね。
子: そう!「伝えたい世界がある」って思っている子には、創造表現学部は最高の舞台だよ!
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。




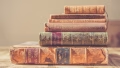
コメント