「工学部」って?“社会の土台”を支える実践派エンジニアを育てる場所
親: 工学部って、いわゆる「ものづくり」の学部でしょ?でも、実際にはどんなことを学ぶの?
子: 確かに「ものづくり」は大事な軸だけど、それだけじゃなくて、「社会のインフラをどうつくるか」「環境を守りながら技術をどう使うか」みたいに、“持続可能な社会”全体を支える技術と知識を学ぶのが滋賀県立大学の工学部なんだ。
親: 地元の公立大学だからこそ、“地域とのつながり”が強いんじゃない?
子: そのとおり!滋賀県や琵琶湖と深く関わりながら、“現場に近い学び”ができるのが最大の特徴だよ。
工学部の3学科構成|それぞれの強みとつながりを活かす横断的な学び
材料科学科
- ナノテク・高分子・セラミックスなど、最先端の材料開発を学ぶ
- 自動車・航空・バイオ・エネルギー分野に応用できる知識を習得
- 材料の構造、性能、安全性、環境負荷を多角的に考察する力を育成
機械システム工学科
- 機械設計、制御、流体力学、ロボット、エネルギーシステムなどを学ぶ
- CAEやCADなどの設計技術や、3Dプリンタ・IoTへの対応力も重視
- 産業界と連携したPBL(課題解決型学習)で、現実の課題に取り組む力を養う
環境建設工学科
- 環境に配慮したまちづくり・防災・インフラ整備をテーマに学修
- 都市計画、地盤・構造解析、水環境、防災工学、再生可能エネルギーにも対応
- 琵琶湖や滋賀県の課題と直結した「地域型工学」が学べるのが魅力
子: それぞれ専門は違うけど、「人と自然と社会をどう支えるか」っていう共通のテーマがあるんだ。
親: 技術だけじゃなく、社会との接点を持って学ぶスタイルなのね。
実験・演習・プロジェクトベースの“手を動かす”学びが充実
- 1年次から製図・基礎実験を通して“ものづくり脳”を養成
- 各学科で設計・解析・開発・試作までを実際に行う実験が多数
- 地域企業と連携したPBLや、琵琶湖をテーマにした環境実習もあり
- ロボットコンテスト、建築設計コンペ、卒業研究展示などアウトプットの場も豊富
- 少人数制+ゼミ制度で、教員からの丁寧な技術指導が受けられる
子: 試験だけじゃなくて、「実際に作って・試して・壊して・直す」ってサイクルを経験できるよ!
親: 現場で必要な“実践力”が、ちゃんと大学の中で身につけられるのは強いわね。
学生の雰囲気は?まじめで実直、“地域と社会に役立ちたい”気持ちが強い
- 工学系らしく理数に強いが、堅苦しさはなく、素朴で落ち着いた学生が多い
- グループワークや地域活動を通して、協調性や対話力も自然と身につく
- 公務員・地元就職志向が強く、“地に足のついた将来設計”ができている
- 部活や地域ボランティアに参加しながら、生活と学びのバランスを取る子も多数
- 教員との距離も近く、「相談しやすい」「応援してくれる」環境が好評
子: 一人で黙々…じゃなくて、仲間と一緒に“本気でつくる”楽しさがあるんだよね。
親: 技術者って無口な印象があったけど、ここでは“コミュニケーション力のある技術者”が育ちそうね。
卒業後の進路は?地元企業・インフラ関連・公務員まで幅広く活躍
主な進路先
- 地元・関西圏の製造業(機械・自動車・電機・精密機器)
- 建設会社・建設コンサルタント・設計事務所
- 環境エンジニアリング企業・水処理・インフラ保全業界
- 地方自治体(技術職公務員・土木・環境保全担当)
- 大学院進学(滋賀県立大、他大学、国公立院への進学実績も)
活かせる資格・スキル
- 技術士補(卒業時取得可能)、土木施工管理技士、環境計量士
- 機械設計技術者、CAD利用技術者、建設系資格など
- MATLAB、SolidWorks、Python、流体解析ツールなど実務で活きるスキル
親: 公立大ならではの地元密着力と、技術者としての確かな専門性が両立してるのね。
子: 「地元で、技術で、社会に貢献したい」って子にピッタリだよ!
保護者の方へ〜どんなお子さんに向いている?
- 機械や建設、エネルギー、環境など理系分野に興味がある子
- 自分の手で作ったものを形にしたい・動かしたいという意欲がある子
- 地域に貢献する仕事がしたい、公務員にも関心がある子
- 理系だけど、人と関わりながら学ぶことが好きな子
- 実験・実習・実社会での課題解決を通して学びたい子
子: “一生モノの技術”を身につけて、“社会に貢献できる技術者”になりたいって思うなら、最高の環境だよ!
親: 公立大の強みと、実践的な教育のバランスが取れた、堅実で頼もしい学部だと感じました。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。

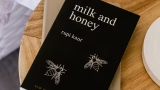



コメント