「環境科学部」って?自然と人間社会の“持続可能な共生”を学ぶ場所
親: 環境科学部って、なんだか時代に合ってる感じがするけど、実際にはどんなことを学ぶのかしら?
子: 滋賀県立大学の環境科学部は、「人と自然がどう共存するか」をテーマに、生態・資源・エネルギー・都市・社会制度まで、環境に関わる幅広い分野を学ぶ学部なんだ。フィールドでの体験や地域との連携も多くて、まさに“実践的な環境教育”が特徴だよ。
親: 単なる理系の勉強じゃなくて、社会のことも学べるってこと?
子: そう!理系と文系の要素を融合させながら、「持続可能な社会づくり」を目指す人にぴったりの学びだよ。
3つのコースで学びを深める|自然・資源・社会の視点から環境を捉える
● 環境生態学コース
- 森林・水辺・里山などの自然生態系を調査・保全する
- 動植物の分布調査や生態系モニタリングを通じて、自然との関わり方を学ぶ
- 野外実習やGIS(地理情報システム)を活用した研究が盛ん
● 環境建築デザインコース
- 自然との調和を重視した建築・都市計画を考える
- 環境配慮型住宅、自然エネルギーの活用、地域の空間デザインを実践的に学習
- 建築士の受験資格取得にも対応
● 資源循環学コース
- 廃棄物・水資源・エネルギーの“循環”と“再利用”を追究
- バイオマス・再エネ・ライフサイクルアセスメントなど、環境工学系のテーマに強い
- 地域の企業や行政と連携した実証研究も豊富
子: 「自然を見る力」「建てる力」「循環をつくる力」。この3つを柱に、“地域と地球の課題”に向き合ってる学部なんだ。
実験・調査・地域連携が主役!机の上だけで終わらない実践型教育
● フィールドを重視した実習の数々
- 琵琶湖の水質・生態調査
- 滋賀県内の里山や森林での継続的な植生観測
- 地元の町や村と連携した空き家・土地活用プロジェクト
- 木材の再利用、地域エネルギーの導入支援
● 実験・設計・分析スキルも強化
- 土壌分析・化学的水質評価・微生物実験など
- 建築設計ソフト(CAD)・GIS・統計処理ツールを使いこなす演習
- 実験レポート・プレゼン・政策提言など、発信型の学びが多い
親: ほんとに“体を動かして学ぶ”って感じね。大学っぽくないくらい、現場感があるわ。
子: そうそう!だから社会に出てからの「即戦力」になるんだよ。
学生の雰囲気|自然派・地域志向・やさしさと行動力をあわせ持つタイプが多い
- キャンパスは緑豊かでのびのびした雰囲気
- 環境問題に本気で取り組みたい学生が全国から集まっている
- 地域のイベントや研究会に積極的に参加する“行動派”が多数
- 素朴で協力的、対話を大切にする温かい空気感
就職・進路|“環境×社会”の力を活かして広く活躍
● 主な就職先
- 地方自治体(環境・都市計画・建築関係)
- 環境コンサルタント会社
- 建設・住宅メーカー(環境デザイン系)
- エネルギー関連企業・再生可能エネルギー事業
- NPO・地域おこし協力隊・環境教育施設
- 大学院進学(滋賀県立大学・京大・東大など)
● 取得可能な資格
- 一級・二級建築士(環境建築デザインコース)
- 環境計量士/公害防止管理者
- 中学校・高等学校教諭免許(理科・地学等)※コースにより
保護者の方へ|どんな子におすすめ?
- 自然や地域のことが好きで、フィールドでの活動が得意な子
- 環境問題に関心があり、社会を変える行動をしたい子
- ものづくりや建築・エネルギーに興味がある子
- 地域貢献や社会課題解決に意欲のある子
- 理系・文系の枠にとらわれず、多角的に学びたい子
子: 滋賀県立大の環境科学部は、「環境系って何を学ぶの?」って聞かれることが多いけど、実は**“社会のど真ん中”にある学問**なんだよ。
親: 地に足をつけて、でも地球規模で考える。そんな学びができるのは、本当に素敵ね。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
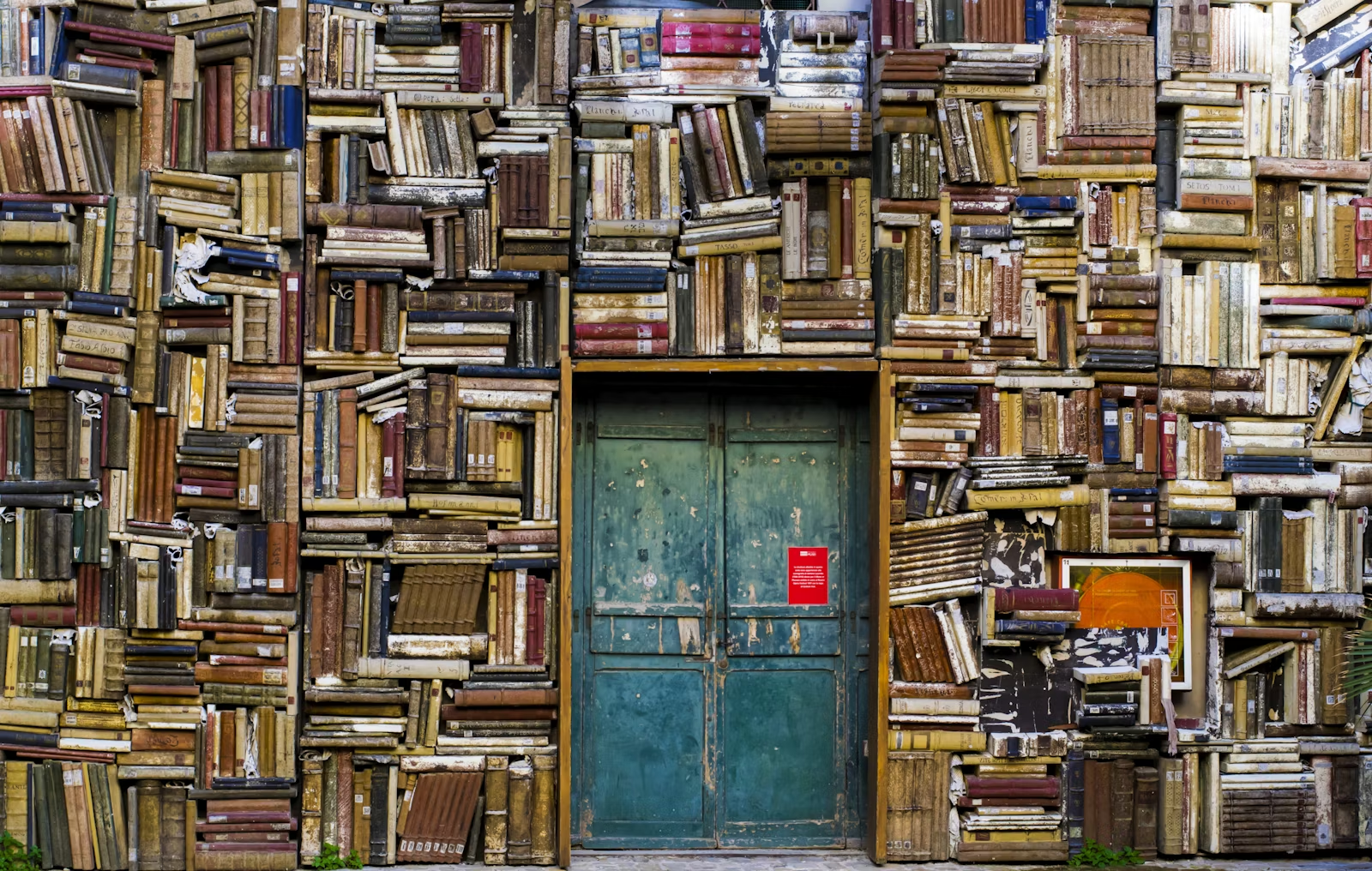
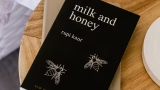



コメント