「国際共創学部」って?グローバルな視点で地域と世界をつなぐ学び
親: 「国際共創」って、ちょっと聞き慣れない言葉だけど、どんな学部なの?
子: 一言で言うと、世界と地域の課題を自分ごととして捉え、多様な人々と協働しながら解決策を創り出す力を育てる学部なんだ。大阪経済大学の国際共創学部では、海外留学や国内外での実践プログラムを通じて、グローバルな視点とローカルな行動力を兼ね備えた人材を育成するんだよ。
親: なるほど。教室での学びだけでなく、実際の現場での経験も重視しているのね。
子: そう。1年次から海外短期留学が必修で、2年次以降も国内外でのフィールドワークが充実しているんだ。現場での経験を通じて、洞察力や共感力、構想力、実践力を養うことができるんだよ。
学びのポイント|「洞察力」「共感力」「構想力」「実践力」を育むカリキュラム
● 海外短期留学が1年次に必修
- 1年次の春季休業中に、ハワイ大学マノア校への3週間の語学留学を実施。実践的な英語力を身につけるとともに、多文化理解を深める。
● 国内外での実践プログラムが充実
- 2年次の「地域探求型実践プログラム」では、アメリカ(シリコンバレー・ポートランド)やタイ、島根県、高知県などでフィールドワークを実施。現地の自治体や企業、NPOと連携し、社会・経済課題の解決に取り組む。
- 3年次の「プロジェクト型実践プログラム」では、ベトナムを訪問し、現地の政府機関や企業、JICAなどを訪問。実践的な課題解決能力を養う。
● 少人数制の演習(ゼミナール)で学びを深める
- 1年次から4年次まで、各年次に必修の演習科目を配置。少人数制のゼミで、学習面、生活面、就職活動まで一貫してサポート。
- 1年次には「アカデミックスキルⅠ・Ⅱ」を通じて、大学での学び方や思考力、情報活用力を身につける。
カリキュラム構成|基盤科目から専門・発展科目へと段階的に学ぶ
● 基盤科目(1年次)
- 「社会・文化」「経済・経営」の基礎的な知識や技能(語学力・思考力・情報活用力)を学び、グローバルな視点で社会・経済課題を洞察・構想するための基礎力を養う。
● 専門科目(2年次以降)
- 専門知識の基礎を形成する基幹科目と、専門性を高める4つの領域(グローバル文化領域、国際社会領域、政策デザイン領域、社会創造領域)から構成される領域科目を学ぶ。
● 発展科目(3年次以降)
- 共創科目と英語アドバンスト科目に区分。共創科目では現地での体験等を通じて、英語アドバンスト科目ではより高い英語力を身につける。
実践の場|国内外でのフィールドワークを通じて学ぶ
- アメリカ(シリコンバレー・ポートランド)でのイノベーションやまちづくりの現場を学ぶ。
- タイでは、現地の大学や日系企業との連携を通じて、国際ビジネスや文化交流を体験。
- 島根県や高知県では、地域の活性化や防災まちづくりなど、ローカルな課題に取り組む。
- ベトナムでは、急速な経済成長を遂げる新興国の現状を学び、国際協力やビジネスの視点から課題解決に挑む。
学生の雰囲気|多様性と協働を重視する学びのコミュニティ
- 多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、互いに刺激し合いながら学ぶ。
- 海外留学やフィールドワークを通じて、異文化理解やコミュニケーション能力を高める。
- 少人数制のゼミで、教員との距離が近く、学習面や生活面でのサポートが充実。
就職・進路|グローバルな視点と実践力を活かして多様な進路へ
● 主な進路
- 企業のグローバル部門・企画部門・営業部門、貿易業や総合商社、旅行代理業など。
- NPO・NGO、外資系企業、国家公務員・地方公務員など、国際社会や地域社会に貢献する職種。
● 資格取得・支援体制
- 中学校教諭一種免許状(英語)、高等学校教諭一種免許状(英語)、社会福祉主事(任用資格)などの取得が可能。
- キャリア支援課による個別相談や就職支援プログラムが充実。
保護者の方へ|こんなお子さんにおすすめです
- 世界や地域の課題に関心があり、多様な人々と協働して解決策を創り出したい子。
- 実践的な英語力を身につけ、国際的な舞台で活躍したい子。
- 海外留学やフィールドワークを通じて、実践的な経験を積みたい子。
- グローバルな視点とローカルな行動力を兼ね備えた人材として成長したい子。
子: 国際共創学部での学びを通じて、世界と地域の架け橋となる人材を目指したいんだ。
親: 多様な経験を積みながら、実践力を養える環境が整っているのは心強いわね。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
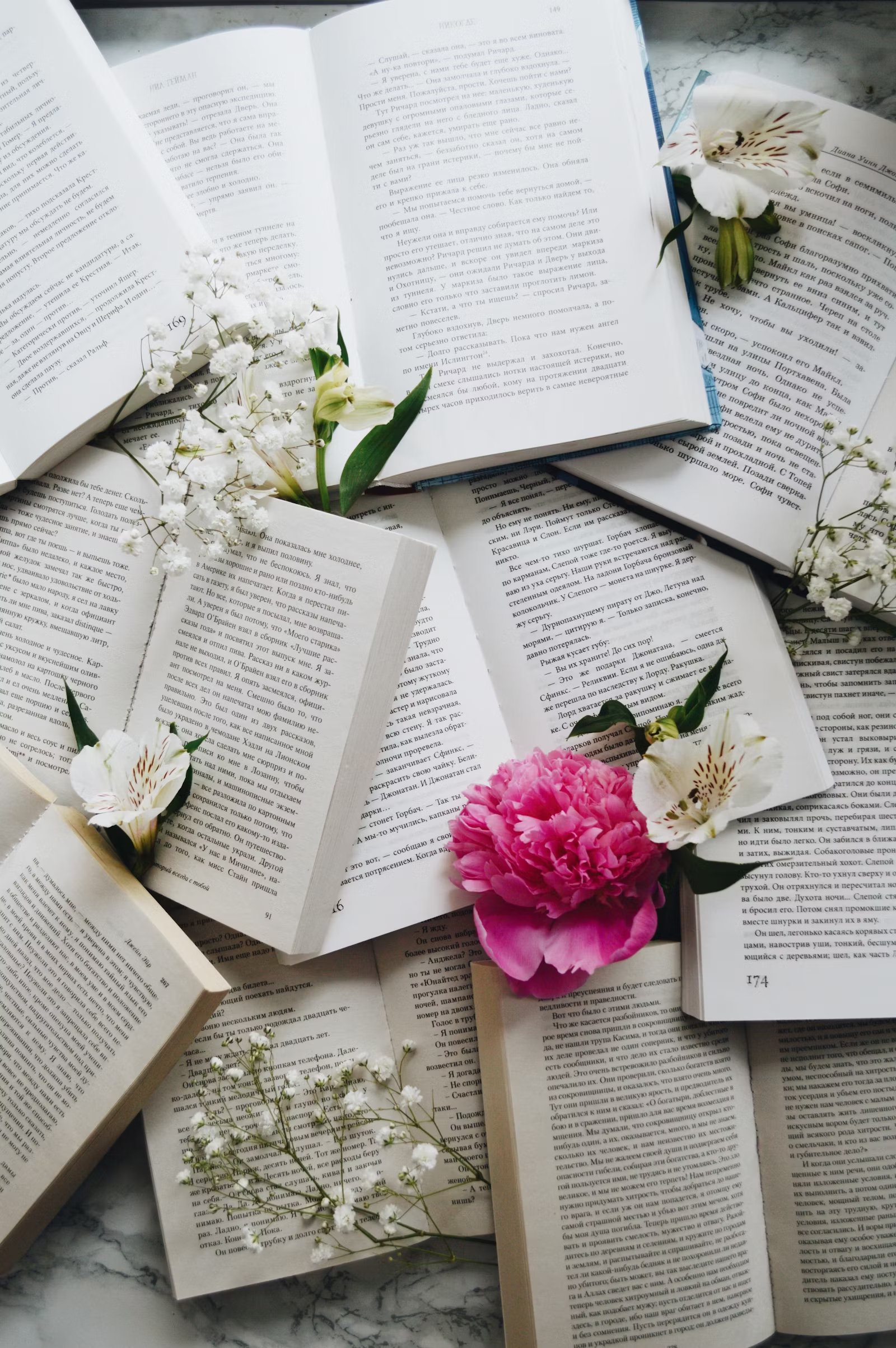




コメント