「社会学部」って? 社会の見えない“仕組み”と“つながり”を発見する学び
親: 社会学部って、ざっくり“社会のことを学ぶ”っていうイメージだけど、具体的にはどんなことを勉強するの?
子: 四国学院大学の社会学部では、社会の中にある課題や仕組み、人と人との関係性を、福祉・地域・メディア・国際文化などの切り口から多面的に学んでいくんだ。単に知識を得るだけじゃなくて、実際に“社会の中に出ていって体験しながら学ぶ”スタイルが中心なんだよ。
親: 机の上だけじゃなくて、フィールドに出る学びって、今の時代に合ってる感じね。
子: うん。人口減少や高齢化、貧困、地域衰退、SNSによる人間関係の変化など、いま社会が抱えるリアルな問題に向き合いながら、“じゃあ自分に何ができる?”を考えることがこの学部の特徴なんだ。
学部の特徴|社会を“知る・感じる・変える”ための実践的な社会学
● 4つの主なテーマで社会を多角的に探究
- 地域社会:まちづくり、移住支援、商店街の再生、地域福祉
- 社会福祉:高齢者・障害者支援、貧困対策、ジェンダー問題
- メディアと表現:SNS、映像、地域PR、情報リテラシー
- 国際文化と共生:異文化理解、移民問題、国際ボランティア
学生はこれらを組み合わせながら、自分の関心のあるテーマを自由に深めていきます。
● 実践重視の「フィールドワーク型教育」
- 地域住民との交流、NPOインターン、ボランティア活動を通じて現場で学ぶ
- インタビュー調査・街歩き・ワークショップ運営など、手を動かす授業が多い
- 「地域を教室に」「社会を教材に」がモットー
● 少人数制で学生の個性と関心を尊重
- 一人ひとりの関心を大切にするカリキュラム設計
- 教員との距離が近く、ゼミや授業での丁寧なサポートが魅力
- 学びの自由度が高く、「自分だけの社会学」がつくれる
学びの流れ|現場での発見を通じて社会への理解を深める4年間
● 1年次:社会学の基礎とフィールド感覚を身につける
- 社会学入門、社会調査法、地域社会論などを学び、土台を築く
- 地域探訪、現地聞き取り調査、実際の街づくり活動などに参加
- グループワークや対話型授業が中心で、考える力と表現力を養う
● 2年次:関心のあるテーマを選び、実践を深める
- 地域福祉、メディア文化論、国際協力入門など専門科目が本格化
- ゼミナールに所属し、調査や企画を学生主体で実行
- 地元団体との連携プロジェクトにも参加し始める
● 3年次:より高度な分析と社会提案へステップアップ
- 社会調査実習(アンケート設計・インタビュー・分析)を実施
- 「調べて終わり」ではなく、調べたことを元に「社会への提案」まで考える
- 海外短期研修や都市部へのフィールドワークなど選択肢も広がる
● 4年次:卒業研究と進路形成の集大成
- 卒業論文テーマ例:「地方都市の若者流出とUターン支援」「SNS時代のつながりのかたち」「外国人住民と地域共生」など
- 自分で課題を設定し、現場調査・理論分析・提案を経て成果をまとめる
- 就職・進学・NPO起業など多様な進路を教員が個別にサポート
学生の雰囲気|「人と関わることが好き」「社会を変えたい」仲間が集まる
- おしゃべりが好きで、人との関わりを大切にする学生が多い
- 地元を大事にしたい、地域に貢献したいという志を持った学生も多い
- 福祉や教育、メディアや表現に興味を持つ子が集まり、個性が光る
- 積極性と協調性の両方を兼ね備えた、あたたかい空気感
主な進路|「人と社会」をつなぐ仕事で広く活躍できる
● 主な就職先
- 公務員(市役所、地域振興課、社会福祉課など)
- 社会福祉法人/地域包括支援センター/NPO法人
- 教育・保育関連施設/児童館/学童保育支援員
- メディア系企業(広告・広報・出版など)
- 一般企業(営業・人事・企画職など、対人スキル重視の業種)
- 大学院進学(社会学、社会福祉学、地域政策など)
● 対応資格
- 社会調査士(社会調査協会認定)
- 社会福祉主事任用資格(所定科目修了者)
- 司書・学芸員課程にも対応(希望者)
保護者の方へ|どんな子に向いている?
- 社会の出来事やニュースに関心があり、「なぜ?」と考えるクセがある子
- 人と関わるのが好きで、対話を通じて学びを深めたい子
- 福祉・教育・地域づくり・国際協力など社会貢献に興味がある子
- 自分なりのテーマや関心をじっくり育てたい子
- 将来の職業選択に柔軟性を持たせながら、社会で役立つ力を育てたい子
子: 社会学って、“人間をまるごと理解しようとする学問”なんだなって感じたよ。
親: どんな仕事でも“人と社会を理解する力”って必要よね。社会学部の学びは、応用範囲が本当に広いわ。
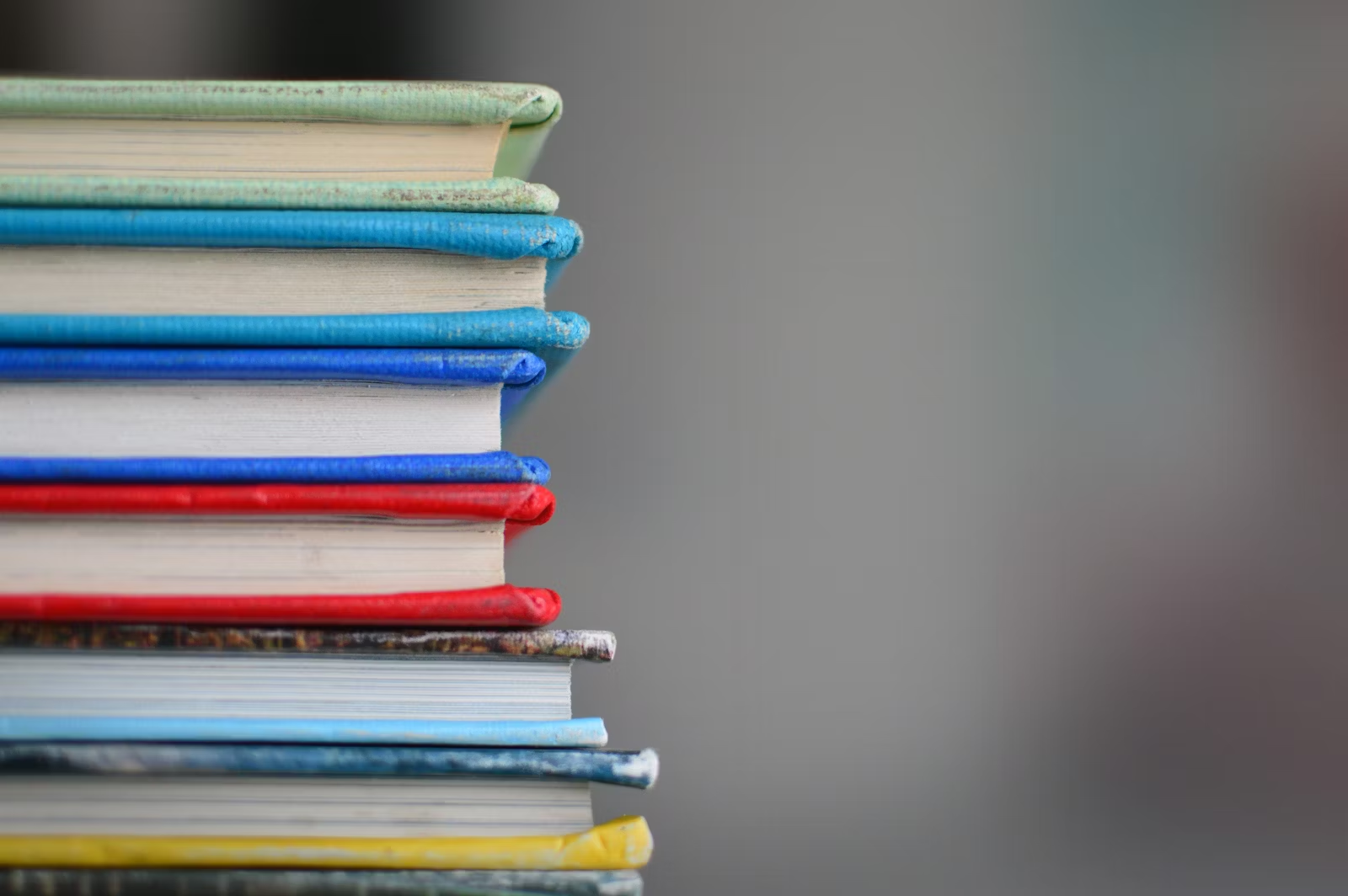



コメント