「医療学部」って? “支える医療”のプロを育てる学びの場
親: 医療学部って、いわゆる「お医者さんを目指す学部」ではないのよね?
子: うん、東亜大学の医療学部では「支える医療」に関わる専門職、たとえば理学療法士・作業療法士・臨床工学技士を目指す学部なんだ。手術をした患者さんのリハビリや、人工呼吸器・透析装置の操作など、病院の中で“欠かせないけど見えにくい”重要な仕事を担う人たちを育てる場所なんだよ。
親: 医師や看護師のように目立たなくても、医療を支えるために必要不可欠な仕事なのね。
子: そう。まさに“チーム医療”の中心的な存在。医療学部では、知識や技術だけでなく、患者さんに寄り添う心や、他の職種と協力する力も大事にして学んでいくんだ。
東亜大学 医療学部の特徴|「高度専門職」と「地域医療人材」を育てる実践教育
● 3つの専門分野で医療現場を支える力を育成
- 理学療法学専攻:運動療法・物理療法を中心に、ケガや手術後のリハビリを担当
- 作業療法学専攻:日常生活動作(食事・着替え・入浴など)を支援し、生活の質を高める
- 臨床工学専攻:生命維持装置(人工呼吸器・透析装置・心肺補助装置など)を操作・保守管理する専門職
● 地域医療との密接な連携
- 山口県・下関市の病院・福祉施設と連携した臨床実習・ボランティア活動が豊富
- 高齢化が進む地域で、“住み慣れたまちで暮らし続ける”を支える多職種連携の実践力を磨く
- 災害時対応、地域リハビリテーションなど、将来を見据えた学びも充実
● 国家資格取得を全力で支援
- 専門科目+国家試験対策講座+個別フォロー体制
- 過去問題演習・模試・個人面談を繰り返しながら「全員合格」をめざす
- 卒業後も学内の「キャリア・国家試験サポートセンター」が継続支援
学びの流れ|基礎から実習、そして現場対応力へと育つ4年間
● 1年次:医学基礎+ヒューマンケアへの理解
- 解剖学・生理学・心理学・看護学概論などの共通科目を学ぶ
- 他専攻の学生と合同授業で“多職種連携”の基礎を体験
- 早期から地域見学・高齢者施設での体験型授業を実施
● 2年次:専門知識と基礎技術を習得
- 各専攻ごとに専門的な実技・演習がスタート
- 理学療法:関節可動域訓練、筋力増強訓練など
- 作業療法:調理・手工芸・日常生活動作の支援方法など
- 臨床工学:人工呼吸器や心電図モニターの操作・管理の実習など
● 3年次:臨地実習で“本物の現場”に触れる
- 病院や施設での長期実習(例:リハビリ病棟・手術室・ICU・透析センターなど)
- 患者さんへの接し方、記録のとり方、チームとの連携方法を実践的に学ぶ
- 実習先での経験を、学内でのフィードバック授業でふりかえり、課題と成長を可視化
● 4年次:統合実習+卒業研究+国家試験対策
- 最終実習で“総合力”を問われる現場体験
- 自分の専攻テーマに基づいた卒業研究(例:高齢者のバランス能力と転倒予防など)
- 個別国家試験対策+グループ模擬試験で合格力を仕上げる
学生の雰囲気|まじめであたたかく、支え合いながら成長する空気感
- 医療職をめざす目的意識の高い学生が多い
- 実習や勉強は大変でも、同じ目標に向かう仲間としてのつながりが強い
- 先生との距離も近く、気軽に相談できる体制が安心感につながっている
- 地元出身の学生と他県からの学生が混ざり合い、多様性と協調性のある雰囲気
主な進路|病院・施設・地域・工学系企業など幅広い選択肢
● 就職先の例
- 病院(急性期・回復期・療養型)
- リハビリセンター・整形外科クリニック・高齢者施設
- 人工透析クリニック・循環器センター・手術室(臨床工学系)
- 医療機器メーカー・福祉用具開発企業
- 大学院進学や医療系教員への道も
● 取得可能な資格
- 理学療法士(国家資格)
- 作業療法士(国家資格)
- 臨床工学技士(国家資格)
- 福祉住環境コーディネーター、医療情報技師(任意資格)など
保護者の方へ|どんな子に向いている?
- 人の役に立つ仕事に就きたいという気持ちがある子
- 身体のしくみや医療に興味があり、専門性を身につけたい子
- チームで協力しながら学ぶことが好きな子
- 地元や地域社会の支え手になりたいと考えている子
- 国家資格取得を通して安定したキャリアを築きたい子
子: 医療って、“診る人”と“支える人”がいないと成り立たないんだって、実習でよくわかったよ。
親: 確かに、命を支える仕事はたくさんあって、どれも欠けたら困るものね。支える力って、本当に尊いわね。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
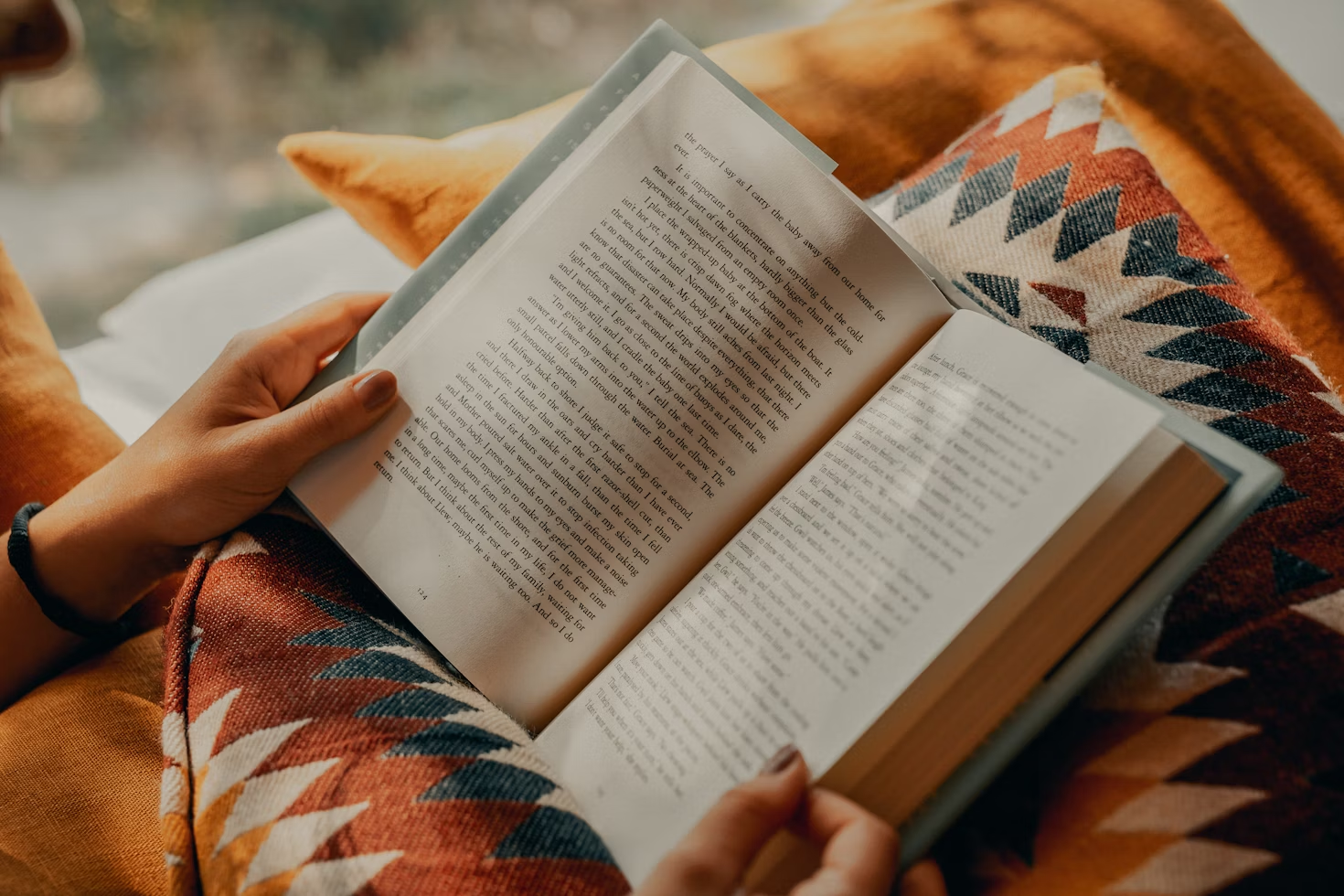




コメント