「こども教育学部」って?“子どもと未来”を育てるプロを目指す学び
親: 「こども教育」って、保育とか小学校の先生になるための学部ってことでいいのかしら?
子: うん、でもそれだけじゃないんだ。鈴鹿大学のこども教育学部では、子どもたちの“今”と“未来”に寄り添える教育者や保育者を育てる学びをしてるんだよ。実習や地域との交流がすごく多くて、机の上だけじゃない“本物の現場”での学びが充実してるんだ。
親: たしかに、今の子どもは色々な課題もあるし、知識だけじゃなくて心の力も必要よね。
学びの特徴|保育・教育・子ども支援を実践的に学ぶ4年間
● 教育・保育の専門知識と実践力を養う
- 教育原理、発達心理学、児童理解、保育内容総論など、基礎からじっくり
- 小学校・幼稚園・保育園の教育課程の違いや連携も体系的に理解
- 教職課程のほかに、子どもの福祉や障がい理解なども幅広くカバー
● 子どもと関わる現場体験が豊富
- 1年次から幼稚園・保育園・子育て支援施設での「見学実習」あり
- 2〜3年次では小学校での教育実習、保育実習、児童福祉施設での体験を段階的に実施
- 三重県・鈴鹿市内の多くの教育機関と連携し、実習先が豊富
● 地域連携・プロジェクト型授業も多数
- 地元の子育てイベントを学生が企画・運営
- 高齢者施設との世代間交流プログラムなども学生が担当
- 地域の課題を子ども目線で捉え、教育・福祉で応答する力を育てる
学びのステップ|「見る」→「ふれる」→「教える」へと成長する4年間
● 1年次:子どもを見る目を育てる
- 教育学・保育学の基礎、子どもの発達段階の理解
- 教育現場の見学や観察記録の演習
- 地域の子育て支援活動への参加
● 2年次:子どもとふれあう経験を重ねる
- 幼稚園・保育所での部分実習、小学校での教育補助活動
- 指導案作成・授業模擬・保育記録演習などの実技中心の授業
- ピアノ、読み聞かせ、手遊びなどの実践スキルを磨く
● 3年次:教壇・保育現場に立ち、指導者の視点へ
- 小学校教員養成課程:2週間〜3週間の教育実習
- 保育士・幼稚園教諭課程:通年を通して施設実習あり
- 各自の進路にあわせたゼミ活動で研究テーマに取り組む
● 4年次:卒業研究と進路確定へ
- 卒論テーマ例:発達障がい児の支援、保育現場における多文化共生、絵本と情緒発達の関係など
- 公務員試験対策や採用試験対策講座も充実
- 教育委員会や現職の先生との面接練習・模擬授業あり
子どもと地域とともに学ぶ“現場直結型”の実習が魅力
- 地元保育園での連携保育実践(季節行事・おたのしみ会の企画運営)
- 鈴鹿市内の小学校での授業づくり・補助・ふりかえりを実体験
- 子育て支援NPOや児童館でのボランティア活動
- 子ども食堂・外国籍家庭の支援など、多様な家庭と接する活動もあり
子: ほんとに子どもと関わる機会が多いから、知識だけじゃなく、**「どう関わるか」**を体で覚えられるんだよ。
学生の雰囲気|やさしさと責任感を持った未来の教育者たち
- 子ども好きな学生が多く、あたたかい雰囲気
- 真面目でコツコツ努力型が多く、協力し合える仲間たち
- 実習やピアノなど苦手を乗り越えようと頑張る姿勢が目立つ
- 地域のお祭りや子育てイベントにも積極的に参加する行動力あり
就職・進路|教員・保育士だけじゃない、多様なキャリアの道
● 主な進路先
- 公立・私立の小学校教諭
- 幼稚園教諭・保育士(市町村・民間施設)
- 児童養護施設・発達支援センター・福祉施設
- 教育系NPO・自治体の子育て支援部門
- 一般企業の教育・福祉関連部門など
● 資格取得支援・試験対策
- 小学校教諭一種免許状
- 幼稚園教諭一種免許状
- 保育士資格
- 公務員試験対策講座(筆記・面接・模擬授業)
- 教員採用試験合格に向けた少人数指導と模試制度
子: 教員になる人もいれば、保育士、子ども支援の福祉職に行く人もいるよ。子どもと関わる仕事の選択肢が広いのがこの学部のいいところ。
親: 安心して子どもを預けられる人になるには、しっかり学ぶ姿勢と、あたたかさが必要ね。
保護者の方へ|こんなお子さんにおすすめです
- 子どもが好きで、成長を支える仕事に興味がある子
- 教育や保育に関心があり、将来は先生や保育士になりたいと考えている子
- 人と関わるのが得意、またはそれを伸ばしたいと思っている子
- 地域や社会とのつながりの中で学びたい子
- 実践を通して“やりがい”や“自分らしさ”を見つけたい子
子: この4年間で、子どもへの思いがもっと深くなったし、「私は教育を通して社会に貢献できる」って思えるようになったよ。
親: 教室だけじゃなく、地域で育ち、地域を育てる。そんな学びができる大学って、今どき貴重かもしれないね。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
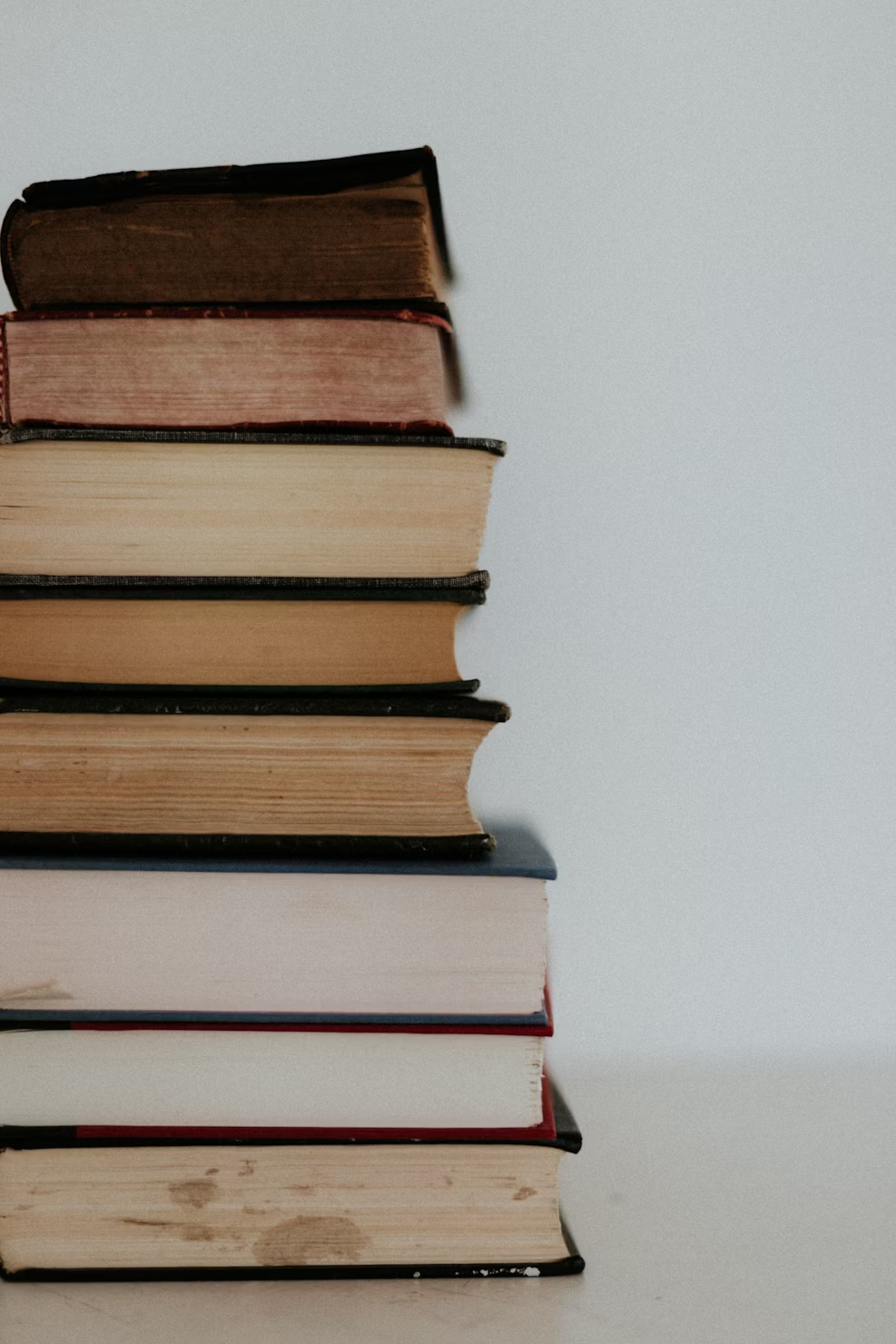




コメント