「生物産業学部」ってどんな学部?場所はどこ?
親: 「生物産業学部」って聞き慣れない名前ね。農学部やバイオ系とは違うの?
子: ちょっとユニークだよね。でも中身は、農学・水産・森林・食品・環境など、“生物資源を産業として活かす”ことを幅広く学べる学部だよ。そして特徴的なのが、**北海道のオホーツクキャンパス(網走市)**にあること!
親: えっ、北海道に行くの!?東京農大なのに?
子: そう(笑)。東京農大の中で唯一、キャンパスが東京ではなくて地方にあるのがこの学部。でもそのぶん、「自然と社会のリアルな関係」を学べるフィールドがすぐそばにあるんだ。
学科はどう分かれているの?水産?森林?食品?
親: 学部の中には、どんな学科があるの?
子: 生物産業学部には以下の3学科があるよ:
- 海洋水産学科:水産資源の管理、養殖、海洋環境、水産経済などを学ぶ
- 食品産業学科:食品製造、流通、地域ブランド、6次産業化などの実学分野
- 森林総合科学科:森林環境、木材利用、野生動物管理、里山づくりなど
親: 漁業も林業も食品産業も扱うのね。まさに“地域の生物産業”!
子: そう!しかもオホーツク海の豊かな自然環境がすぐ近くにあるから、すごく実践的な学びができるんだ。
授業や実習はどんな感じ?現場に強いの?
親: 北海道ってことは、やっぱり現地実習が多いの?
子: すごく多いよ!たとえば、水産学科では網走湖やオホーツク海での調査、食品産業学科では地元企業と連携した商品開発、森林学科では山林での伐採実習や野生動物調査がある。机の上だけじゃなく、“フィールドで学ぶ”のが当たり前な学部なんだ。
親: 自然の中で学ぶって、ちょっとワクワクするわね。
子: うん、「体験を通して考える」ことが大事にされてて、実社会との接点も多いから学びが深いよ!
学生の雰囲気は?地方ならでは?
親: 網走って聞くと、ちょっと遠いし寒そうだし、学生生活が心配だけど…
子: たしかに冬は寒いけど、学生の雰囲気はとってもあったかいよ!地方出身の子も多くて、のんびりした子や自然が好きな子が多い。みんな助け合って暮らしてる感じ。寮や下宿も充実してるし、学年を超えたつながりもあるから安心して生活できるよ。
親: 地方だからこそ、人の距離が近いのかもね。
子: うん、まさに「地域ぐるみで学ぶ」っていう雰囲気があるよ!
就職はどう?北海道に残る人が多い?
親: 就職先はどんなところ?北海道に残るの?
子: 北海道で就職する人もいるけど、全国に広がってるよ。水産系なら水産庁、漁業協同組合、食品系ならメーカーや流通、森林系なら林野庁、林業コンサル、住宅会社など。「現場がわかる理系人材」として、いろんな業界で評価されてるよ!
親: 公務員にもなれるの?
子: なれる!水産・森林系の技術職、公務員(農政、林務、水産)に強くて、地域振興系の仕事にも進んでる人が多い。最近は観光やまちづくり系にも広がってきてるよ。
主な進路実績:
- 水産庁、農林水産省、環境省など技術系官公庁
- 地方自治体(農政・水産・林務職)
- 食品メーカー・水産加工企業・流通系企業
- 漁協・森林組合・林業事業体
- NPO・地域振興団体
- 大学院進学(資源管理、食品科学、環境系など)
印象に残った授業や実習は?
親: 印象に残ってる授業や体験ってある?
子: 網走湖での漁業体験実習かな。氷の張った湖の上でワカサギ漁を見学して、地元漁師さんと話をして、「漁業って自然と生きる営みなんだ」って実感した。スーパーで魚を買うだけじゃ分からない“命の重み”を感じた経験だったよ。
最後に、保護者の方へ
親: 北海道まで行かせるのはちょっと不安もあるけど、自然の中での学びには魅力を感じるわ。
子: 東京農大の生物産業学部は、“都市ではできない学び”が詰まってる学部だと思う。食・自然・地域に向き合いながら、これからの日本や世界の持続可能性を考えられる人になれる場所だよ。
親: どんな子に向いてる学部だと思う?
子: 「自然が好き」「地域に貢献したい」「実践を通じて学びたい」――そんな思いがある子には、ほんとにぴったり!“地方でこそ育つ力”を実感できる学部だと思う!
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。




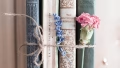
コメント