「生物生産学部」って?“育てる科学”で命と未来を支える学び
親: 「生物生産学部」って、農学部とは違うの?何を勉強するの?
子: 農学部に近いけど、広島大学の生物生産学部は農業・水産・バイオ・環境・食料問題など、「育てて、活かす」ことに特化した学部なんだよ。海・陸・微生物、いろんな“いのち”にアプローチできるんだ。
親: 食料や自然に関わる学問って、これからますます大切になりそうね。
子: うん。持続可能な社会づくりにも直結してるし、地球規模の課題に“現場と研究”の両面から向き合えるのが魅力なんだ。
学びの柱|「いのちを育てる・守る・つなぐ」ための3分野
● 動物・水圏生物生産
・魚や家畜などの生産と健康管理、育種、栄養学などを学ぶ
・水産学・畜産学の両面に対応。養殖や漁業資源の管理も重視
・生態系への配慮やバイオ技術を活かした新しい育種法も探求
● 植物・農業生産
・作物の栽培、生理、品種改良、病害虫対策、環境適応などを学ぶ
・有機農業やスマート農業といった新しい生産技術にも対応
・里山・地域農業との連携で実践的な体験が可能
● 応用生物科学・バイオテクノロジー
・微生物の働きを活かした発酵、環境浄化、遺伝子操作など
・食品開発・資源循環・環境修復など幅広い応用が可能
・DNA解析・バイオリアクターなどの最先端設備も使用
学びの流れ|フィールドとラボを行き来する4年間
● 1年次:自然科学と生物生産の基礎を学ぶ
・生物学・化学・物理などの理系基礎+生産系の入門科目を学習
・農場見学・海洋調査など、早期から現場とつながる授業もあり
・レポート作成や実験手法の基礎を固める
● 2年次:専門分野の学習と実習の本格化
・動物・植物・微生物・水圏など、それぞれの分野に分かれて専門科目を履修
・栽培・飼育・遺伝・環境など、多様な実験とフィールドワークを経験
・データ収集・分析力を養う演習も充実
● 3年次:研究室に所属し、探究を深める
・ゼミ形式で自分の研究テーマを設定し、観察・実験・分析を行う
・農業・水産・食品・環境分野のプロと協働する実地研究も可能
・インターンや地域プロジェクトなど学外活動も活発化
● 4年次:卒業研究と進路形成
・卒業研究に本格的に取り組み、成果をまとめて発表
・大学院進学、食品企業、地方公務員など進路に応じた個別指導あり
・研究成果を地域や業界と共有する発表会も開催
実践の場|“現場での学び”を大切にするカリキュラム
- 附属農場・水産実験場での実地実習(植物栽培・魚類養殖など)
- フィールドワーク(干潟調査、海洋観測、土壌分析など)
- 地元の農業法人や食品企業との連携インターンシップ
- 発酵・微生物応用実験(ヨーグルト・納豆・環境バイオ)
- プレゼン・論文作成演習も段階的に実施
子: 机の上の勉強だけじゃなくて、「土をさわって」「水に入って」「菌を育てて」って、五感で学べるのがこの学部の魅力!
学生の雰囲気|自然や命にやさしい、まじめで温厚なタイプが多い
- 動植物や微生物に興味のある、やさしく観察好きな学生が多い
- 実験や栽培など“手を動かす”学びが好きなタイプ
- 地道な作業も前向きに取り組める、真面目で誠実な雰囲気
- 農業・水産・環境などに「社会貢献」の意識を持つ学生も多い
就職・進路|“育てる・活かす・支える”多様な仕事へ
● 主な進路
・食品・農業・水産・環境関連企業(商品開発、品質管理、研究職など)
・公務員(農業普及員、水産技術職、環境行政など)
・地方自治体や農協・農業法人
・大学院進学(農学・環境・生命科学分野など)
・高校理科教員、バイオ技術者、研究開発職など
● 資格・支援制度
・中学・高校教諭一種免許状(理科)取得可能
・食品衛生管理者・環境計量士など、受験対応科目あり
・キャリアセンターによる面接対策・インターン紹介も充実
・農業・バイオ業界のOB/OG講演なども定期開催
保護者の方へ|どんなお子さんに向いている?
- 動物・植物・微生物など“いのち”に関心がある子
- 自然や食べ物に興味があり、育てることが好きな子
- 環境問題や食料問題に対して、実践的に学びたい子
- 地域社会や人の暮らしに役立つ学びをしたい子
- 実験・栽培・観察など、手を動かすことに楽しさを感じる子
親: 「育てる」って、地味に見えて実はとてもクリエイティブな仕事なのね。
子: うん。知識だけじゃなくて、手と感覚と経験で学ぶ“リアルな科学”を実感できる場所だよ。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
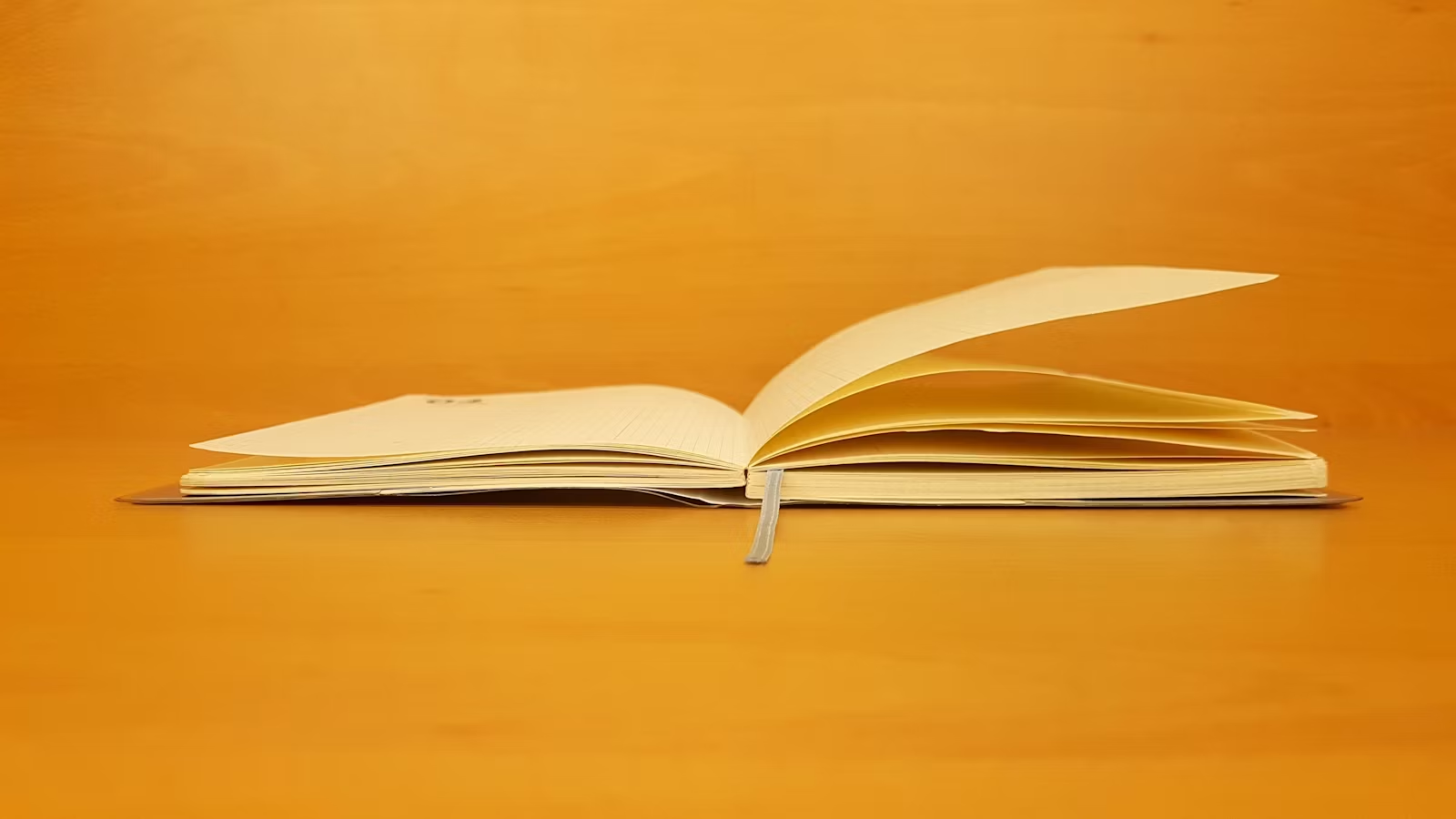




コメント