「健康科学部」って?“こころとからだと暮らし”を支える学際的な学びの場
親: 「健康科学部」って名前は聞いたことあるけど、看護とかスポーツとは違うの?どんなことを学ぶの?
子: 広島国際大学の健康科学部は、「病気を治す」じゃなくて、「病気にならない社会をつくる」ための学びが中心なんだ。つまり、予防・支援・啓発を通じて、人の健康と生活を支える人材を育てる学部なんだよ。
親: 医療とも福祉とも教育ともつながりがあるってこと?
子: まさにそう!心理・保健・生活支援・地域連携・社会制度の知識を横断的に学んで、人と社会の“健康”を幅広くサポートする力を育てていくんだ。
学びの柱|「支える」「つなぐ」「育てる」の3つのアプローチ
● 支える:健康を広くとらえる「人間理解と支援力」
- 心理学、社会福祉学、教育学、栄養学、発達学などを土台に
- 子ども・障がい者・高齢者など、あらゆる人の“暮らしの健康”を支える視点を養う
- 個別支援+集団支援のバランス感覚を育成
● つなぐ:多職種連携・地域連携で「現場に通じる実践力」
- 医療、福祉、教育など**分野横断的な学び(学際教育)**を重視
- 保健所・地域包括支援センター・行政・学校・企業との連携授業が充実
- 「自分一人で抱え込まない」「専門家と協働する」ための思考を身につける
● 育てる:予防・啓発・教育で「人と社会の未来を変える力」
- 公衆衛生、健康教育、ヘルスプロモーション論など
- 子育て支援/生活習慣病予防/孤独対策など社会的テーマにも対応
- 健康イベントの企画運営、パンフレット制作、地域講座でアウトリーチ実践
学びの流れ|「広く学ぶ→深く考える→実践する→伝える」の4年間
● 1年次:健康と社会の全体像を理解する
- 健康科学入門/人間発達/心理・福祉の基礎理論を学ぶ
- 医療制度・社会保障・地域福祉の仕組みも体系的に理解
- グループワーク中心で、“チーム支援”の視点を育む
● 2年次:支援と連携の技術を磨く
- ケーススタディ/ロールプレイ/コミュニケーション演習が充実
- 保健活動、健康教育、カウンセリング技法の初歩なども導入
- 行政・NPO・施設でのフィールドワークや課題解決演習がスタート
● 3年次:現場体験と専門性の探究
- 地域福祉センター・保健所・教育現場での中長期実習を実施
- 専門ゼミに所属し、「孤立する高齢者支援」「産後うつ予防」「こども食堂の運営」など
→ 実践と調査を行いながら、自分のテーマを深める - 他学部との連携授業もあり、「看護師と連携して地域を支える」などの視点も学ぶ
● 4年次:卒業研究・政策提言・キャリア支援の総まとめ
- 実地調査・インタビュー・文献分析を活用し、卒業論文を作成
- 地域や大学主催の公開発表会でプレゼンする機会も多数
- 公務員・企業・大学院など、それぞれの進路に応じた個別指導を実施
実践の場|“地域とつながる”を体で学ぶプロジェクト型授業
- 行政と連携した地域健康フェスタの企画運営(学生主体)
- 発達障がい支援団体と共同での「保護者向けパンフレット制作」
- 高齢者サロンでの健康体操・認知症予防ワークショップ
- 中高生へのストレスマネジメント講座を学生が実施
- 地域包括支援センターと行う生活相談シミュレーション演習
子: ここでは、ただ知識を学ぶだけじゃなくて、「誰に、どんな方法で、どう伝えるか」まで考える力がつくんだ。
親: 健康って病院で治すだけじゃないのね。“暮らしの中で守る力”が大事なのね。
学生の雰囲気|「人の話をよく聞ける」「まじめでやさしい」タイプが多い
- 自分の意見を押しつけない、「寄り添う姿勢」を大事にする子が多い
- 現場主義の授業が多く、課題解決にじっくり向き合う風土
- プレゼン・発表にも慣れていて、発信力のある学生が育っている
- 心理・教育・福祉・医療など、進路も多彩なため、お互いの視野を広げ合える環境
就職・進路|“社会のつなぎ役”として多分野で活躍!
● 主な進路
- 【行政】市町村の保健福祉職/地域包括支援センター職員/健康推進課など
- 【企業】福祉用具メーカー/保険会社の健康支援部門/健康サービス系ベンチャー
- 【教育・支援】発達支援センター職員/保育支援員/放課後等デイサービス職員
- 【福祉・医療連携】社会福祉法人/クリニックの地域連携室/健康管理センター
- 【大学院進学】社会福祉学/公衆衛生学/教育学/心理系などへの進学多数
● 取得を目指せる資格・支援
- 社会福祉主事任用資格
- 認定心理士(条件付き)
- 地域ケア関連研修/ヘルスプロモーター研修/公務員試験対策講座
- キャリアセンターとゼミ教員が連携して、進路指導を“二重体制”でサポート
保護者の方へ|どんなお子さんに向いている?
- 人と関わるのが好きで、誰かの力になりたいと願っている子
- 医療・福祉・教育の現場を支えたいと考えている子
- 心理・支援・地域貢献といったテーマに関心がある子
- 将来は「人の健康や生活の質を支える」実感のある仕事に就きたい子
- 社会の仕組みを理解して、“橋渡し役”として働きたい子
親: 健康って、病気になってからじゃ遅いのよね。こういう人がもっと必要とされる時代なのね。
子: うん。“健康を守る”って、「そばにいる人の毎日を支えること」なんだなって、ここで気づいたんだ。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
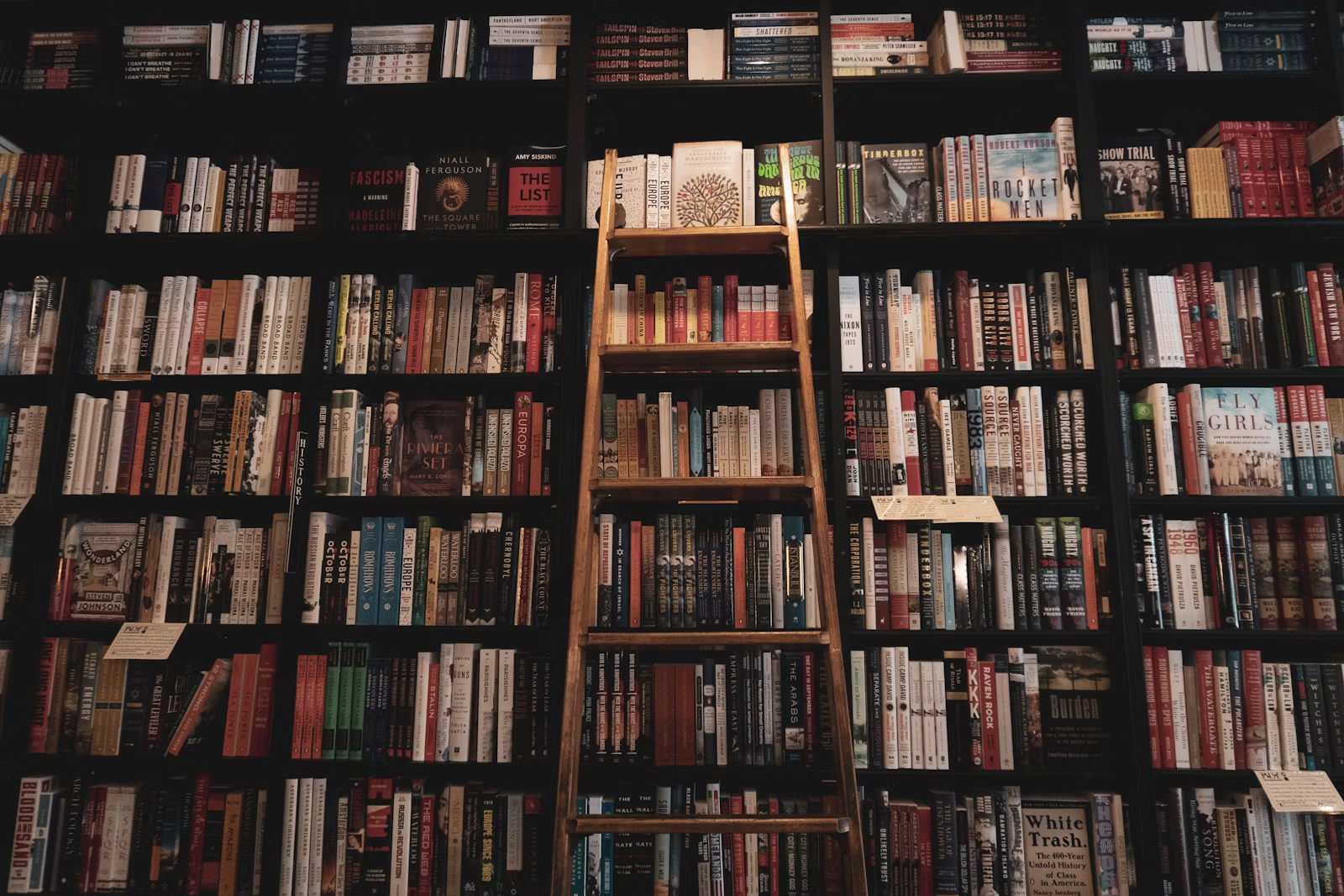




コメント