「システム工学群」って?未来を支える“賢い技術”を学ぶ場所
親: 「システム工学群」って、ちょっと難しそうな名前だけど、どんなことを学ぶの?
子: 一言で言うと、「社会をより便利に、安全に、スマートに動かす技術」を学ぶんだ。AIやロボット、自動運転、エネルギー制御など、現代の社会インフラを支える“頭脳的な工学”が中心なんだよ。
親: モノを作るだけじゃなくて、それをどう動かすか・制御するかってことね。
子: そうそう。たとえばロボットを作るだけじゃなくて、それを“どう動かせば安全か”“どう学習させるか”って仕組みまで考えるのがシステム工学なんだ。
学びの特徴|「つくる」だけじゃない、「動かす・考える」技術者を育てる
● 分野横断型の工学教育
- AI・数理モデリング・ロボティクス・エネルギー制御など多彩な学び
- 情報系・機械系・電気電子系の融合的カリキュラム
- 将来の変化に柔軟に対応できる“学際型エンジニア”を育成
● 実験・プロジェクト重視の実践教育
- 1年次からプログラミングやロボット制御の実習あり
- チームでのものづくり・課題解決型演習が豊富
- 学内外のコンテストや産学連携プロジェクトにも参加可能
● 数理的思考・シミュレーション力の育成
- 数学や物理を“現象を説明し、解決する道具”として活用
- モデル化→解析→実装まで一貫して学ぶ構成
- 複雑な社会課題に「しくみ」で挑む能力を養成
学びのステップ|数理と実践のバランスでスキルを積み上げる4年間
● 1年次:基礎力と問題発見力をつける
- 工学基礎(数学・物理・情報)+プログラミング入門
- 「課題解決演習」でモノづくり・チーム活動に早くから取り組む
- 自分の興味分野を探る探究型授業も実施
● 2年次:システム思考と応用力の育成
- 制御工学・電気電子回路・機械設計・AI概論などを体系的に学ぶ
- ソフトウェアとハードウェア両方の視点を持つ技術者へ
- ミニプロジェクトで試行錯誤とプレゼン経験を積む
● 3年次:専門性の深化とプロジェクト型学習
- ロボティクス、画像認識、エネルギーシステムなど応用分野へ
- 企業・研究機関との共同プロジェクトや学外実習の機会あり
- 配属された研究室で、個別テーマに本格的に取り組み始める
● 4年次:卒業研究と実社会への応用
- 研究成果の発表・論文執筆・学会参加なども経験可能
- 社会実装を見据えたプロトタイピングやソリューション提案
- 就職活動や大学院進学に向けたキャリア支援も充実
実践の舞台|「現場に活かす」リアルな工学プロジェクト
- 学生が設計したロボットで競う「ロボコン」への参加
- 地元企業と共同開発したスマート農業システム
- 自動運転モデルカーの開発プロジェクト
- AIを活用した交通シミュレーション研究
- 再生可能エネルギーを利用した省エネシステムの提案
子: 作って終わりじゃなくて、「どう役立つか」「どう人を助けるか」まで考えるのが面白いんだよ。
学生の雰囲気|探究心と実行力のある“考えて動ける”仲間たち
- 機械やAIに興味がある“理系好き”な学生が中心
- 積極的に手を動かして試す“ものづくり体質”が強い
- 課題解決やチームワークに前向きな人が多い
- 教員との距離が近く、研究・進路相談も親身に対応してくれる
- 地方出身者と全国からの進学者が混ざり合い、程よいアットホーム感
就職・進路|社会の“しくみ”を支える技術者として多方面に活躍
● 主な進路
- 製造業(自動車、電機、ロボット、機械設計など)
- IT業界(ソフトウェア開発、AIエンジニア、システム設計)
- 通信・インフラ系企業(ネットワーク、センサー技術)
- 公務員(技術職)、インフラ系企業
- 大学院進学(高知工科大学大学院含む)
● 就職支援体制
- 専門教員による研究・就職両面でのサポート
- インターンシップの機会多数(県内企業とも強く連携)
- 学内での企業説明会・OB訪問制度なども充実
保護者の方へ|どんな子におすすめ?
- ロボットやAIなど、最先端技術に興味がある子
- モノづくりやプログラミングが好きな子
- 数学・物理が得意、または好きな子
- 実験・実習で“体で覚える”タイプの学びが合っている子
- 地域や社会の課題を“技術の力”で解決したいという気持ちがある子
子: “技術=工具”じゃなくて、“技術=考える力”って感じ。問題をどうとらえて、どう解決するかが問われるんだよ。
親: 技術を使って社会に貢献する。そんな未来を見据えた学びができる学部なのね。頼もしいわ。
本記事は、早稲田大学国際教養学部に在籍し、進学塾を主宰する筆者が保護者の方に向けて執筆しました。内容は2024年度時点の情報をもとにしています。最新情報は大学公式サイトをご確認ください。
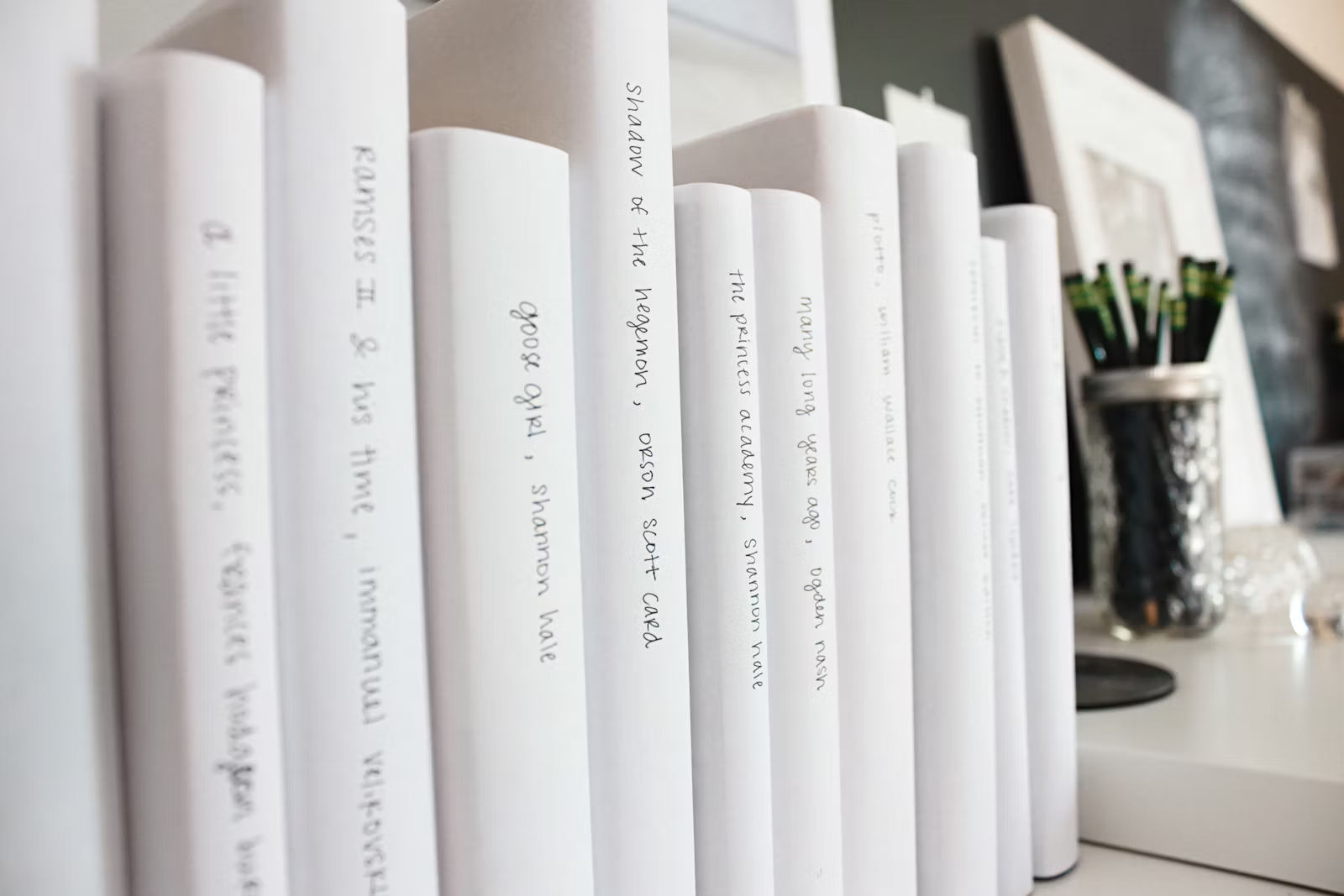




コメント